 自己紹介
自己紹介
略歴
秦 順一(はた じゅんいち)
- 1940年9月9日
- 京都市に生まれる
- 1966年4月
- 慶應義塾大学医学部卒
- 1975年4月
- 東海大学医学部病理学助教授
- 1982年5月より
- スウェーデン王立カロリンスカ研究所客員研究員
- 1984年10月
- 国立小児病院小児医療研究センター病理病態研究部長
- 1990年4月
- 慶應義塾大学教授(医学部病理学)
- 2001年4月
- 国立小児病院小児医療研究センター長
- 2002年3月
- 国立成育医療センター研究所長
- 2005年4月
- 国立成育医療センター総長(2007年3月まで)
- 2007年4月
- 国立成育医療センター名誉総長 慶應義塾大学名誉教授
- 2008年4月
- 常磐大学人間科学部教授
- 2008年9月
- 常磐大学大学院人間科学研究科教授を兼ねる
- 2013年4月
- 公益財団法人 実験動物中央研究所 所長(2020年6月まで)
- 2020年4月
- 星槎大学客員教授
- 2021年7月
- 公益財団法人 実験動物中央研究所 特別顧問
- 2024年4月
- 公益財団法人 実中研 特別顧問(研究所名変更)
社会活動など
(NPO法人)小児がん治療開発サポート(SUCCESS)理事長など
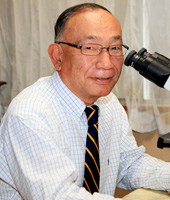
生い立ち
少し長くなりますが、こどもたちや孫など私の後に続くものに自分がどのような背景で世に出たのかを少しでもわかるように私の生い立ちを詳しく述べたいと思います。
私は1940年(昭和15年)に京都で生まれました。
父方は京都出身、母方は大阪出身で、両方とも祖父が医者をしていました。父方の祖父は北里柴三郎とともに日本医師会の創設に力を尽くした人で、日本の医学の創生期に活躍した産婦人科医だったということです。
父方祖父には13人の子どもがいました。父はその12番目で1910年(明治43年3月16日)に生まれています。岩手医科大学(当時は医学専門学校)の第1回生です。卒業後京都大学医学部耳鼻咽喉科学教室へ入局し、当時の前橋赤十字病院などへ赴任しています。
やはり耳鼻咽喉科の医師でした。
母方の祖父は現在の兵庫県相生市出身です。母はその長女として1914年(大正3年4月9日)に生まれ、兄弟3人(私からは叔父)がいました。
大学を出てすぐに軍医として従軍し、激戦地の満州で戦闘に巻き込まれ負傷もしたようです。
幼き日の戦争経験
父がずっと応召していたため、子どもの頃は母、妹と共に、大阪の母方の祖父母の家で暮らしていました。往診に行くときには祖父専用の車夫が扱う人力車が待っていました。祖父がそれに乗って出かけていくのを、よく見送ったものです。
しかし終戦間近になって関西でも空襲が激しくなり、一九四五年六月の大阪への大空襲で祖父母の家を焼け出され、私たち三人は親戚を頼って神戸の六甲に逃れました。しかし重要な港である神戸への空襲も激しく、その年の八月、大規模な空襲によって親戚の家も焼き出され、雨霰のように焼夷弾が降ってくる中、再び逃げ惑うことになりました。
焼夷弾を落として街を火の海にしたB29は、その後、六甲山に爆弾を落とし、山へ逃げた親戚の一家は全滅しました。
5歳の子どもにとって、焼夷弾の降る中を逃げ惑った上、自分たちはようようのことでなんとか生きているのに、昨日まで同じ家で一緒に暮らしていた親戚や子どもたちが全員、一瞬のうちに死んでしまった、というのは、非常にショックな出来事だったと思います。今でもあの晩の、空から大量に降ってくる焼夷弾、何もかもが燃え上がり、その炎に照らされていた景色は、瞼の裏に焼き付いて強い印象を留めたままです。
今なら、こころの傷を癒す治療が必要だ、と考えるでしょう。
しかし当時は、これが日常でした。多くの人々が同じような経験をし、たぶん人間として大きく傷つきながらも、それを越えて生きることを続けるしか方法がありませんでした。そういう時代だったのです。
このようにして命からがら、私たちは空襲を生き延びました。
終戦後の昭和21年、軍医として応召していた父親が帰国し、しばらくは京都で暮らしていました。父方は京都の出身であり、また父自身も京都の大学を出たのですが、かなり長い間満州で従軍していたため京都に医師としての基盤がなく、結局、その後、東京の病院に嫁いでいる父の姉を頼って、東京に出ることにしました。病院に隣接する場所で、耳鼻咽喉科を開業することになったのです。
父・母、母方の祖父母、叔父、妹
父の復員当時(撮影:1946年)
左より叔父(濱本 卓・母の末弟)、妹(万木千里)、母(秦 いと子)母方・祖母(濱本とく)、母方・祖父(濱本研吉)、私(4歳),父(秦 誠)

母方の祖父、大叔父、大叔母(撮影年:1960年頃?)
左から濱本久代(英次・妻)、濱本とく、濱本英次(祖父・弟),濱本宗俊(祖父・妹)濱本研吉(祖父)

終戦直後の東京は、一面の焼け野原でした。
父の帰還後しばらく住んでいた京都は、戦争直後とは思えないほど平和な雰囲気に満ちていました。空襲も逃れていたし、鴨川がゆったりと流れ、遠くには山が霞み、平安の昔そのままと思われるような空気が流れていました。ところが東京の五反田へ来てみると、焼け野原の埃っぽさ、場末の小便臭さ、人が多くごみごみした様子。京都とのあまりの違いに、子ども心にとても驚いたのを覚えています。
東京へ出てきたとき、私は小学校一年生でした。ほとんどの小学校が焼けて校舎もろくになく、焼け残った学校で授業を行うので、あちこちから大勢の生徒がやって来ます。生徒の数が多いので午前と午後に分けた二部授業を行っていました。
家も親も亡くした子ども、弁当を持ってこられない子ども、傘がないために雨が降ると欠席する子どもなど、大勢いました。みんな何かが欠けていて、すべての物資が不足している。そんな時代だったのです。
研究への第一歩
終戦直後のゴタゴタの中、小学校、中学校、そして都立小山台高校へと進み、大学を選ぶ時期になりました。
私の家は、両親の祖父を初め父、叔父たちなどみな医者です。開業しているもの、大学で教授をやっているものなどさまざまでしたが、ほとんど全員が医学の道に進んでいました。それで大学に行こうとしたとき、みんな医者なんだから自分も当然医者だろう、と安易に考えたのですが、当時も今も医学部は難関です。家族に医者が多いから、などという安易な考えで簡単に入れるわけがありません。結局、回り道をして、慶應義塾大学医学部に入りました。
医学部は、勉強することが山のようにあります。同級生たちは必死に勉強していましたが、私は大学に入学したのを幸いと、夏はサッカー、冬はスキー、運動三昧でした。
結局、六年間、落第はしなかったものの、どう考えても勉強より遊びの方に力が入っていたと思います。そのため、いざ卒業、国家試験に合格して医者になるのだ、となったとき、さすがに「これはまずい」という考えが心に芽生えました。医者になるには少し遊びすぎた、ということにやっと気づいたわけです。
しかし今さらもう一度、授業を受けて勉強をやり直すことはできません。仕方がないので大学院に行き、医学というものを少し深く勉強してみよう、と思いつきました。その上で患者さんを診る臨床に出れば、少しはましな医者になれるだろう、と考えたのです。そのために、基礎医学をみっちり勉強する病理学教室に行く、と決めました。
当時、慶應義塾大学大学院の病理学教室は非常に多士済々で、優秀な先輩が揃っていました。慶應義塾大学では、各学部で一番成績が良い生徒に銀時計を授与するのですが、医学部で銀時計を授与された者はほとんど病理学教室に入る、と言われたほどです。そのような教室だったので、毎年入るのは医学部の中でもとくに優秀な一人か二人。そんな教室に、私たちの学年からは五人も入りました。もちろん私を含めて銀時計などには全く縁がない人間ばかり。先輩からは、病理学教室に初めてタイトルのないヤツが入ってきた、と言われたものでした。
病理学教室では、片っ端から解剖を行い、臓器の細胞を顕微鏡で見つめ続けます。基礎病理学をしっかり身につけた後、それぞれの興味がある分野を専門とするのですが、私の場合は、心臓の奇形をはじめとする発生病理学、腫瘍の発生などにとても興味を引かれました。結局それが、小児病理、中でも小児がんを専門するきっかけになっています。小児病理学を専門にし始めてからは、現在の国立成育医療センターの前身である国立小児病院にも、週に1-2度勉強をしに行きました。
病理を勉強したあと臨床に行こうと思っていましたが、結局、病理にとどまることになりました。とくに臨床に行くことを嫌ったわけではないのですが、その機会を失ってしまったということでしょうか。病理を勉強しているうちに、細胞の発生や分化に興味が湧き、研究そのものがとても面白くなって、そのままずっと患者さんとは顕微鏡を通して向き合いながら、今に至っています。 そんな私の唯一の臨床経験は、インターン時代です。
私たちの時代はちょうどインターン闘争が激しかった頃で、活動の一環として国家試験のボイコットなどもありましたが、インターンそのものは現在のスーパーローテートと同じように全科を廻る研修でした。患者さんと直接向き合う臨床は、病理に進む上で大変有意義な時間を過ごしたと思っています。
システム作りと研究と
病理学教室には、綺羅星のような先輩たちがひしめいていました。教授、助教授、講師という人たち、そしてその予備軍が本当に大勢いました。
私自身は別に偉くなりたいとは思いませんでしたが、上に大勢つっかえているのは鬱陶しい、なんとかならんかな、と思っているとき、先輩の先生から、東海大学の病理の教授として出るけれども一緒に行かないか、というお誘いを受けました。
1970年から5年間ほどの当時は新設医科大の創設ブームで、その流れで東海大学の医学部が創設され、慶応義塾大学から教授を出すことになっていました。渡りに舟と、先輩と共に私も東海大学に移りました。
当時の東海大学は新設されたばかり。病理学がどうとか言う前に、教育のシステムも何も全く整っていませんでした。私たちは白紙の状態のところに、さまざまなシステムを植え付けていきました。医学部の教育システム、病気の研究の基礎、さらに教室全体の設計などにも関わりました。東海大学には九年間在籍しましたが、医学教育や研究の基礎をわれわれが築いたという自負があります。
東海大学のさまざまなシステムや研究の基礎が整った後、私自身は慶応時代と同様、小児がんの研究を続けました。
その頃、デンマークで発見されたヌードマウスが話題になっていました。ヌードマウスは体毛がないのでヌードマウスというのですが、その一番大きな特徴は先天的に胸腺がない、ということです。このヌードマウスは、突然変異で発生したものです。
胸腺という器官は、細胞免疫系で非常に重要なリンパ球の中のT細胞を成熟させるのに、大きな役割を果たしています。ヌードマウスにはこの胸腺がないため、移植免疫の機能が働きません。つまり異種のものを移植しても、免疫機能によって攻撃されることがないわけです。
このネズミを川崎にある実験動物中央研究所の野村達次所長が輸入し、東海大学のわれわれのグループと組んで
ヒトの腫瘍を植え、がん細胞の持つ機能の研究を行いました。今まではがんの研究は主に動物の癌細胞を用いた研究が主体でしたが、ヌードマウスが発見されて、はじめてヒトのがんが実験系にすることができたのです。
しかも、それまでヒトがんの研究は、細胞をバラバラにして試験管の中に入れ、培養細胞としてその性格を調べる、in vitroという方法を取っていました。しかしこのヌードマウスを使えば、試験管の中ではなく生体内で、ヒトのがんの性格を研究することができます。
もちろんヒトの生体ではありませんでしたが、その研究ツールは画期的なものでした。日本では、東海大学と実験動物中央研究所が初めてヒトの腫瘍をヌードマウスを介して実験系にする、というツールを確立しました。私はその方法を用いて小児がんの研究を始めました。
白夜の街で
東海大学のさまざまなシステムも整い、ヌードマウスを使った実験系のがん研究も軌道に乗って自分のことを考える余裕ができた頃、少し違う場所に行って違うことをし、視野を広げたい、と思うようになりました。
あのまま慶應義塾大学の病理学教室にいたら、上に多くの先輩たちがつかえていたので、もっと留学したいと思ったかも知れませんし、また実際、多くの研究者仲間たちは30歳代でアメリカなどに留学し、新しい技術を吸収して帰国後の研究に役立てています。しかし私はちょうどその時期、東海大学の新しいシステム作りに奔走しており、ふと気づいたときには四〇歳を越え、一般的にいう留学の時期を逸していました。
それならそれで、また何か別の発見があるだろうと考え、1982年5月、家族と一緒にスウェーデン王立カロリンスカ研究所への留学しました。留学先にスウェーデンを選んだのは、元々ヨーロッパが好きだったこと、ノーベル賞を持つ国だということ、加えて日本人があまり行かないから、というのが大きな理由です。
語学が苦手な私は、アメリカ英語で話をされると意味が取れず、だいたいアメリカに留学する医者は掃いて捨てるほどいます。後追いで同じ所に行っても仕方がない、それなら人のいかない場所に行った方がいい、というヒネクレ者の考えかたなのかもしれません。
スウェーデンという国は福祉大国として有名ですが、税金が三〇%~四〇%にもなり、政策的にはかなり破綻していました。しかし社会的な福祉や相互協力といった仕組みは非常に充実しており、そのための税金という考えかたが国民の間に浸透しています。
スウェーデンの国民は極めて頑固に理想を追求する性格を持っており、こうあるべきと信じる社会にするためには徹底した合理主義をとります。その一つが、完全なジェンダーの平等です。
スウェーデンでは成人はみな、男性女性に関係なく働いています。カップルはとくに結婚という形を取る必要はなく(もちろん結婚しても良いのですが)、子どもができると母親に対して子どもの養育費が出ます。この形式だと、子どもを産んだ女性がシングルマザーであろうがカップルであろうが、待遇に格差はありません。またカップルで育児休暇を取る場合、男女に関わらず給料の高い方が働き、安い方が休暇を取って育児をします。これなども非常に合理的な形式で、ああ、こういう形があったのか、と目から鱗が落ちる思いでした。
さらに勤務形態も、必ず九時から五時まで週に五日間働く、と決まっているわけではなく、都合のいい時間のパート形式や在宅で働く人も多く、そういう人々に対しても保険などの福利厚生はすべて社員と同様に整っていました。そのようなシステムを見て、社会的にすべてを支えるには、ある程度税金が高くても仕方がないのだと納得したものです。
またスウェーデンには大学の医学部が七つありますが、学生の平均年齢は四〇歳程度です。これは医学部に入学する資格の一つに、会社などに勤務して社会生活を送った経験があることが含まれているためで、医者になるためには通常の大学を出て就業し、社会人としての経験を積んでからでないと、医学部への入学もできないわけです。
この資格制度には、若者が医学部に入ることを阻害しているという意見もありましたが、客観的に見れば、やはり非常に合理的な制度だと思います。確かに長時間の外科的手術を行う場合など、若い方が体力的に有利な分野もありますが、患者さんが老若男女それぞれいて、性格も病気も症状もそれぞれ違うのですから、医者にも若い人、熟年の人、さまざまな経験を積んだ人間がいるべきです。医学には臨床も研究もあり、また病気そのものの研究ばかりでなく疫学的な研究も、その病気を俯瞰的に考えるためにはとても大切なのですから。
留学したカロリンスカ研究所病理学部門では、それまで日本でやっていた研究とは少し分野の異なる、「免疫病理学」という分野の研究に加わりました。当時は、リンパ球には色々な種類があるのだ、ということが解明され始めたところで、実際に行っていたのは電子顕微鏡を使ってリンパ球の微細構造を形態学的に解析する仕事です。
リンパ球の中にはT細胞やB細胞と呼ばれるものがあり、同じT細胞の中にも性格の違うものがあります。ヘルパーT細胞のように免疫を作る際に主導的に働く細胞があるかと思えば、自分の抗体ができると困るのでそれを積極的に殺す役割をするキラーT細胞や、がん細胞を殺すナチュラルキラー細胞もある。このようなリンパ球の中のさまざまな細胞を、それぞれに特異的な抗体を使って染色し、電子顕微鏡で観察してその形態を調べる、というのが仕事の内容でした。
ただこの研究は、非常にユニークなものではあったのですが、それほど最先端というものではありませんでした。そのためゆったりとした研究生活を送ることができ、合間にはしばしば休暇を取って家族と共にヨーロッパ各地を廻っていました。スウェーデンに留学したことの意義は、研究そのものよりもむしろ、スウェーデン社会のさまざまな合理性を経験したこと、そしてノルウェーやフィンランド、デンマークなどの北欧の国々を中心に、ヨーロッパ各国の人々の生活をかいま見られた、ということにあったと思います。
スウェーデンには一年半ほど行っていました。
一番印象的だったのは、やはり冬の日の短さ、夏の白夜に近いほどの日の長さでしょうか。私たちが住んでいたのはストックホルムですが、夏至の頃には夜中でも完全に真っ暗にはなりません。もう少し北の方に行くと完全な白夜になりますが、ストックホルムでは日は沈むものの明るさが残ったまま、また日が昇ってきます。夏も非常に涼しく快適ですが、その代わり冬は暗く寒い日々が続きます。
一緒に行っていた子どもたちは当時、小学校の四年生と六年生でしたが、八月の二〇日頃から新学期が始まります。その頃にはもう、落ち葉が散り始めてリンゴがなり、日が急速に短くなって夜の長い冬がやって来ます。冬の間は明るくなり始めるのが朝の九時半くらい、昼過ぎの二時か三時にはもう暗くなってしまうので、子どもたちは暗いうちに学校に出かけ暗くなってから帰ってくる、という生活でした。
私たちはほんの一年足らずでしたから、東京とは全く異なる冬の生活もそれなりに楽しみましたが、スウェーデンという国の合理的でかつ、ねばり強く頑固に理想を追求する国民性は、あの長く暗く寒い冬を耐えることで培われるのではないかと思っています。
今へと続く道
スウェーデンでの1年半ほどの生活を終えて帰国し、さてこれからどうしようか、と考えていた1984年(昭和59年)10月、成育医療センターの前身である国立小児病院に小児医療研究センターが設立されました。私にとってはまさにグッドタイミングでした。そこで東海大学からそちらに移り、病理病態研究部長という職を得て、本格的に小児がんの研究を始めました。
小児がんの研究といっても色々なアプローチがありますが、私の場合はやはり細胞や遺伝子の解析が中心になります。具体的には、がん由来の幹細胞の分化について仕組みや性格を調べたり、がんを発生させる遺伝子を発見、解析したり、ということを行っていました。しかしながら、私の立場はあくまでも病理学という形態学に根ざした研究を行うことです。形態学的に細胞や組織をじっくり観察して、形態学的変化が生じる原因を遺伝子や分子に求めるという立場で研究を進めてきました。
小児がんは細胞が分化します。先ほど述べた胎児性腫瘍と呼ばれる一群の固形腫瘍は、胎生期の細胞ががん化してできるのですが、そのがん細胞は胎生期に持っていた分化能を持ち続けています。そのために分化するのです。その究極が胎児性がん細胞(EC細胞=Embryoral Calcinoma Cell)と言われる多分化能をもつ幹細胞で、胎盤、神経細胞、筋肉細胞、消化管など、再生医療への研究が行われているES細胞と同様、あらゆる細胞に分化します。
私たちは、精巣にできた腫瘍からこの多分化能を持ったEC細胞を一つ取り出し、そこからどのようなものが分化するのか、また分化に伴ってどのような抗原が出てくるのか、などの研究をしていました。当時はまだES細胞がなったので、ヒト受精卵のモデルとしてはEC細胞が唯一のものでした。
この頃ちょうど、骨髄の中にある間質細胞から取り出された幹細胞が、心筋や骨などさまざまなものに分化する、ということが解明され始めました。こちらはその後、再生医療への利用が進んでいますが、私たちが研究していたEC細胞は元々ががん細胞なので、再生医療に使うことはできません。あくまでもがんの特性や発生の仕組みを解明するための素材としての幹細胞です。
「成育医療」(2007年 悠飛社刊)より
現在に至る
1990年4月に母校の慶應義塾大学医学部病理学教室の教授に就任しました。 当時の教室はまた自分一人で赴任せざるを得なかったことや分子レベルの研究を行う機器も少なく、分化の研究を行う環境ではありませんでした。しかし、幸いなことに若い助手が一緒に研究をすることに同意してくれたこと。また、思いがけなく大きな研究費が得られたので、今までの研究をさらに発展するよう、研究室の整備を行いました。大学院生や他教室からの共同研究者も次第に集まり胎児性癌細胞の分化の研究が進みました。その成果は国際誌に発表するとともに、1998年の春期病理学会総会で宿題報告「胎児性腫瘍の病理」として口演しました。また、小児病理の研究も行いました。2001年4月には春期病理学会総会の総会長をつとめました。
2001年3月に国立成育センター研究所の前身である国立小児病院小児医療研究センターセンター長に就任しました。 その1年後の2002年2月に国立成育センターが設立され、研究所所長に就任しました。研究所は2003年3月に病院のある大蔵に移転し、名実ともにわが国最初の母子に関する医療と研究を行うナショナルセンターとして国立成育医療センターが創設されました。 2005年4月に同総長に就任しました。その間、創成期の国立成育医療センターの円滑な運営を図るとともに小児がんの臨床研究の仕組み、特に中央病理診断の確立につとめました。
2007年3月には国立成育医療研究センター総長を退官し、同センター名誉総長、慶應義塾大学名誉教授の称号を得ました。 2008年4月から水戸市にある常磐大学人間学科部健康栄養学科教授となり、週の半分は水戸で過ごしました。同学科では管理栄養士の国家資格取得を目的とする学生に解剖生理学と病理学を教えました。
人間科学部では様々な分野の文科系教員と交流することができました。特にイタリア美術史を専門とする松原哲也准教授とは公私ともに親しくなり、耕作放置地を借り蕎麦、小麦、馬鈴薯などを栽培し、地域の人たちや学生たちと毎年収穫祭を楽しみました。野鳥の撮影を始めたのもその頃です。松原さんとはイタリアへ旅行し、ルネッサンス初期の絵画に直接接することができました。また、レオナル ド ダヴィンチの手稿について共著の論文も発表しました。
2013年4月には公益財団法人実験動物中央研究所(現実中研)所長に就任しました。実中研は1952年に慶大医学部の大先輩である野村達次先生が設立された医生物学や創薬研究に用いるユニークな実験動物を作製する世界に冠たる研究所です。その中で私は遺伝子改変により作製したマウスのヒト疾患モデルの解析や患者から採取したがん組織を免疫不全マウスに移植して得られるPatient derived xenograft(PDX)を用いてがんの病態を解析する研究に従事しました。
2020年に同研究所所長を辞し、今は特別顧問として引き続きPDXを用いた研究を続けています。


